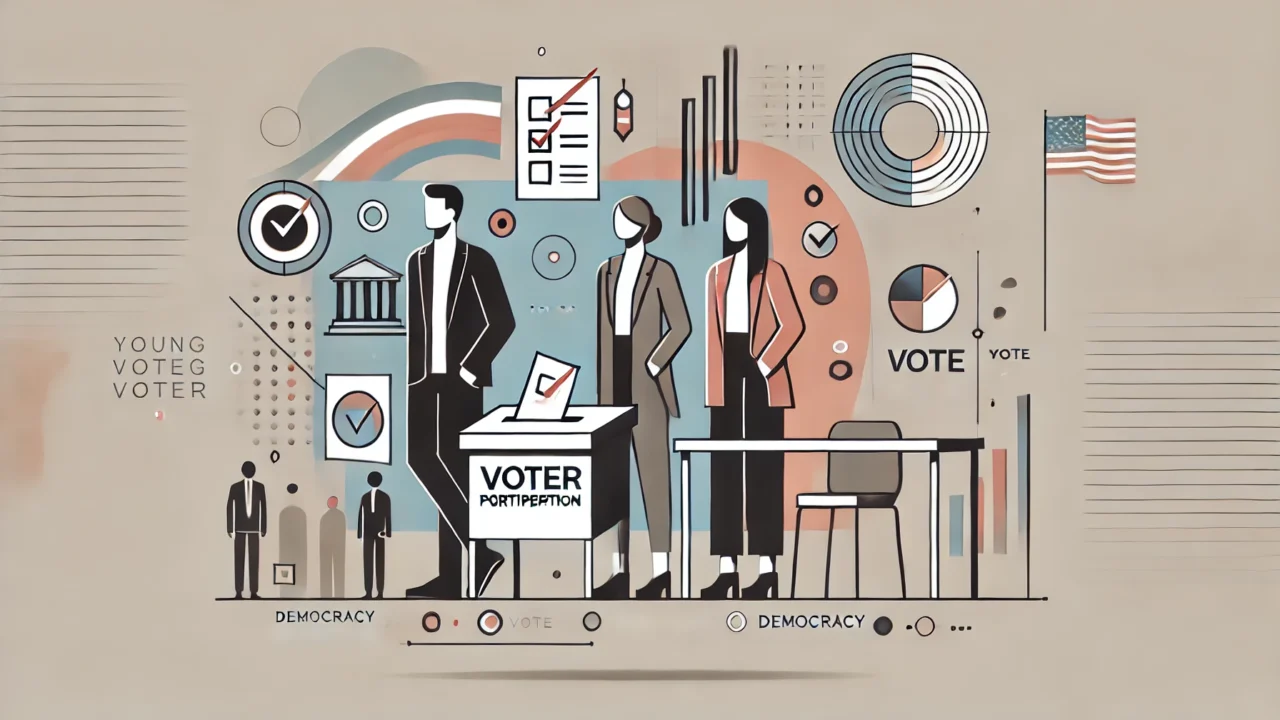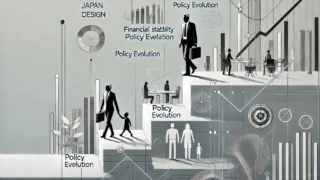若者の投票率が低いのはなぜか?ただの無関心ではない理由
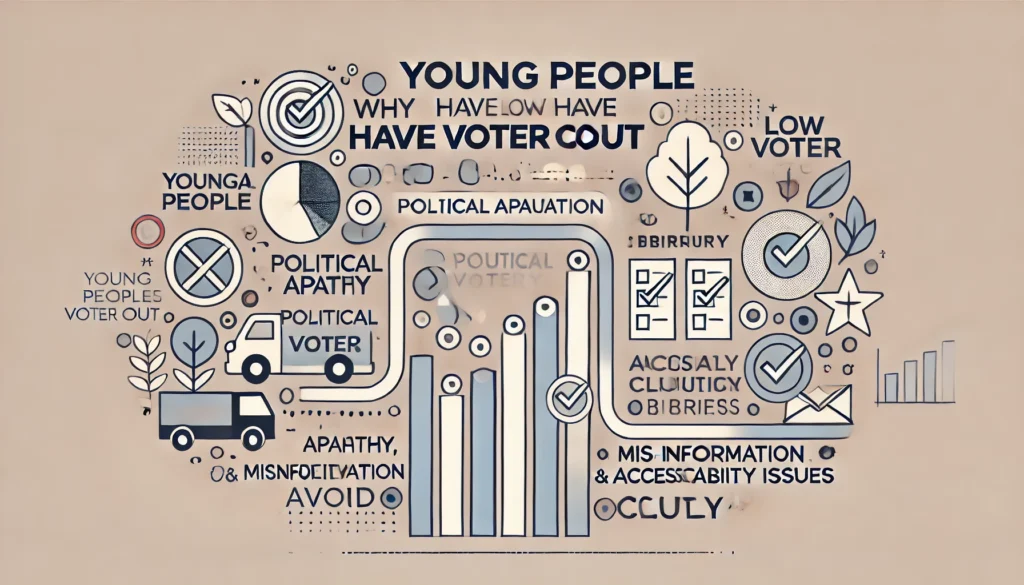
「若者は選挙に行かないからけしからん」という声をよく聞きますが、本当にそうなのでしょうか?若者の投票率が低い背景には、単なる無関心だけでなく、社会や歴史の影響が深く関わっています。
昔は政治が人々の生活に直接影響を与えていたため、若者も政治に対して強い関心を持っていました。しかし、時代の変化とともに「政治が自分たちの生活に関係している」と感じにくくなり、「投票しても何も変わらない」と思う人が増えてしまいました。特に、日本では高齢者の人口が多く、選挙で投票する人の大半が高齢者であるため、「若者の一票はあまり影響がないのでは?」という考えが広がっています。
しかし、若者が投票しないと、政治は高齢者向けの政策ばかりに偏ってしまう可能性があります。だからこそ、「なぜ若者の投票率が低いのか?」を深く理解し、その理由を解決する方法を考えることが重要です。
歴史を振り返ると見えてくる、政治参加の変化

日本の政治と人々の関わり方は、時代とともに変化してきました。1960年代から70年代の高度経済成長期には、政治が経済政策を進め、国民の生活がどんどん豊かになっていました。そのため、多くの人が政治に関心を持ち、選挙に積極的に参加していました。
しかし、1990年代のバブル崩壊をきっかけに、経済が不安定になり、政治家の汚職事件やスキャンダルも増えました。これにより、「政治に期待しても裏切られるだけだ」「自分が投票しても政治は変わらない」という不信感が広がりました。こうした社会の変化が、若者の投票率低下の大きな要因となっています。
また、インターネットやSNSの普及によって、政治に関する情報が増えた一方で、「どの情報が正しいのか?」を判断するのが難しくなりました。結果として、政治に対して距離を置く若者が増えました。
若者の投票率低下の原因と乗り越えるべき課題
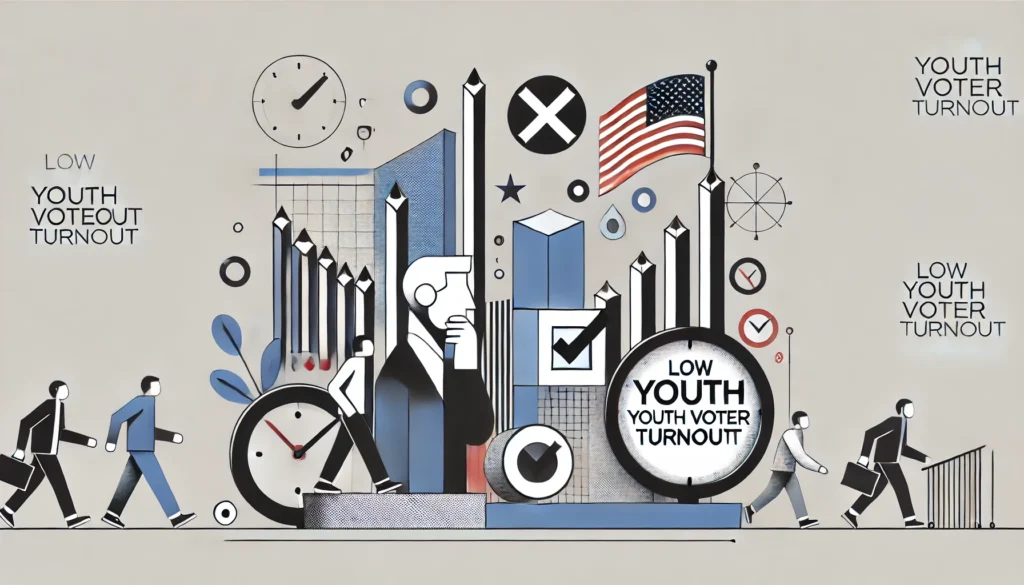
現代社会では、政治や選挙に関する情報が非常に複雑になっています。例えば、選挙の候補者や政策の違いを理解するのは簡単ではありません。さらに、学校では政治について詳しく学ぶ機会が少なく、「そもそも選挙に行く意味がわからない」という人も多いです。
加えて、投票にはいくつかのハードルがあります。例えば、「仕事や学校で忙しくて投票に行く時間がない」「投票所が遠い」「期日前投票のやり方がよくわからない」などの理由で、投票に行かない人が増えています。
また、若者の投票率が低いと、選挙の結果が高齢者の意見に偏りやすくなります。例えば、若者が「社会の変化が必要だ」と思っても、投票率の高い高齢者が現状維持を望めば、大きな変化は起こりにくいのです。このような状況が続くと、「やっぱり投票しても意味がない」と感じる人が増え、さらに投票率が下がるという悪循環が生まれます。
若者の政治参加を促すためにできること

若者の投票率を上げるために、さまざまな取り組みが行われています。その一つが「主権者教育」です。これは、学校で政治や選挙について学ぶ機会を増やし、「投票の重要性」を理解してもらうための教育です。例えば、模擬選挙を行い、実際の選挙の流れを体験できるような取り組みもあります。
また、投票のハードルを下げる工夫も進められています。期日前投票の利用が広がり、仕事や学校が忙しい人でも選挙に参加しやすくなりました。さらに、インターネット投票の導入が検討されており、スマホで簡単に投票できる未来も近づいています。
最近では、SNSを活用して政治をわかりやすく伝える政治家も増えています。例えば、石丸伸二さんや斎藤元彦さんは、SNSを通じて若者と直接コミュニケーションを取り、短期間で大きな影響を与えました。こうした動きが増えれば、「政治は難しいものではなく、自分たちにも関係がある」と感じる若者が増えていくでしょう。
僕自身、若者の投票率が低いことを理由に批判する人たちが、本当に政治の成果を高く評価しているとは思えません。むしろ、世代ごとに責任を押し付け合うのではなく、すべての世代が互いに理解し合い、より良い政治を作ることが重要だと思います。
若者が「自分の意見が政治に反映される」と実感できるような環境を整えれば、将来的には政治全体が変わる可能性があります。投票は未来を作る大切な行動です。「一票では何も変わらない」と思うかもしれませんが、多くの若者がその一票を大切にすれば、確実に社会を変える力になります。