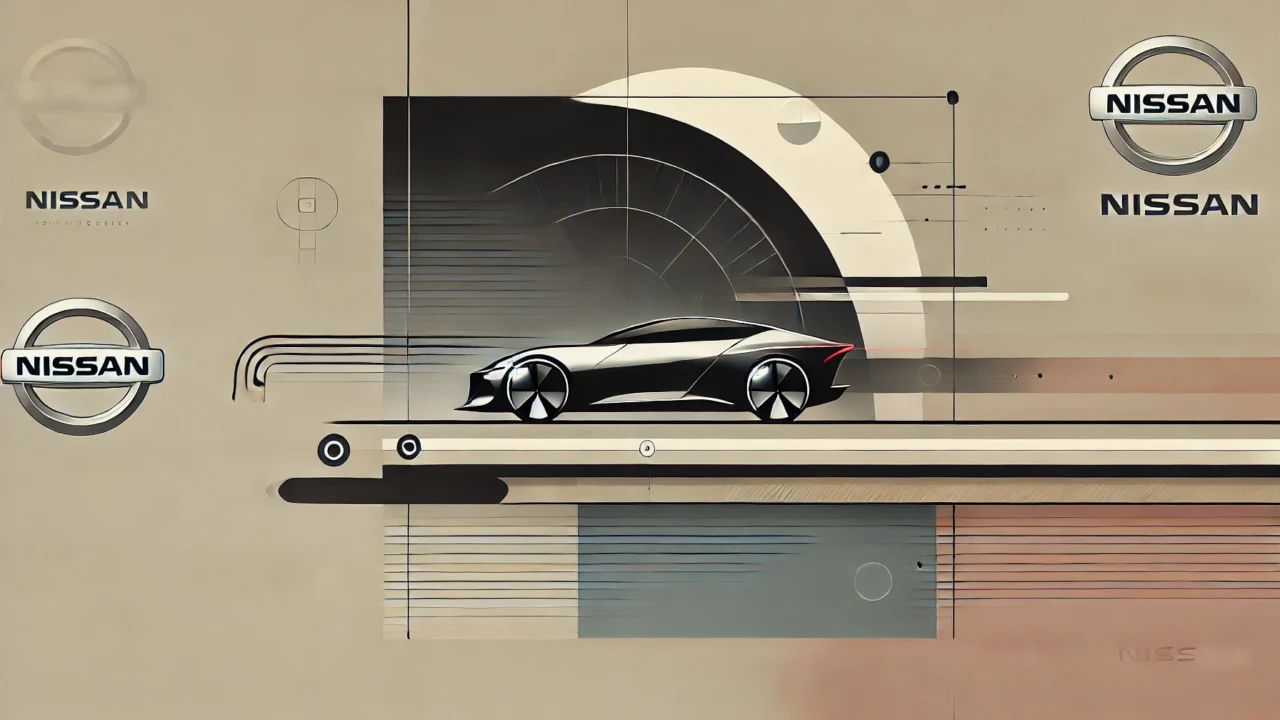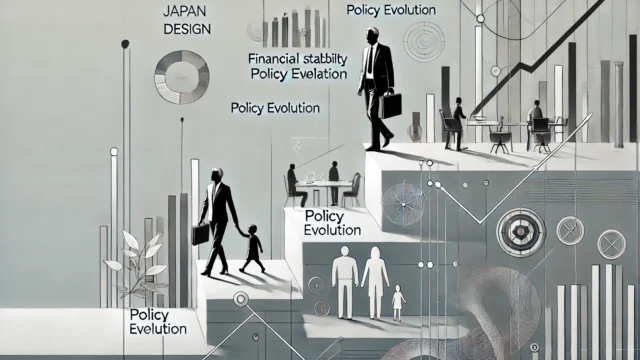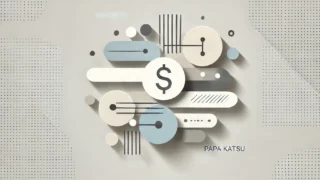日産が誇った「技術の日産」とは?
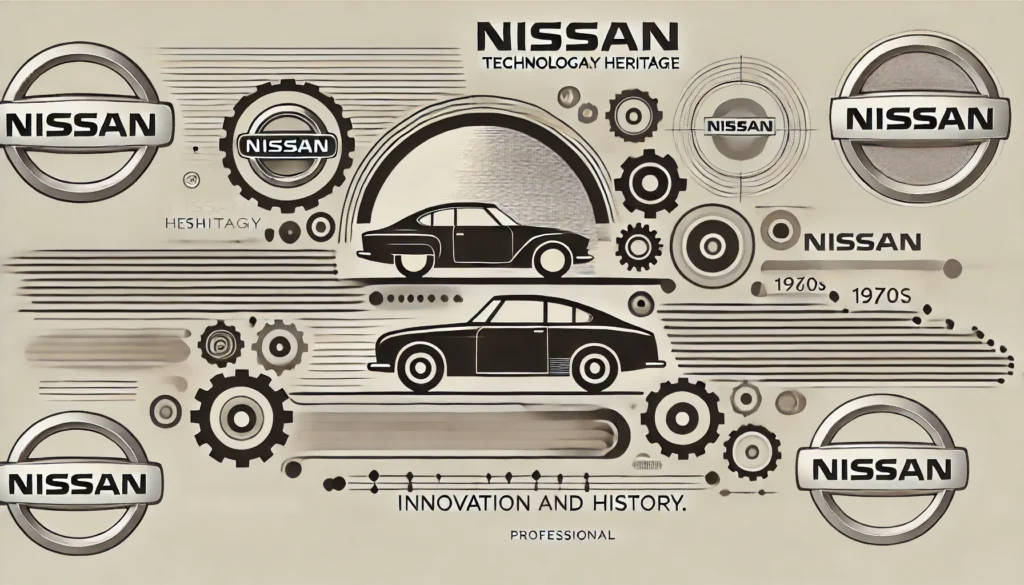
日産自動車は、1960~70年代に「技術の日産」として大きな注目を集めました。特に、省エネルギー設計や独自のエンジン開発で世界を驚かせ、多くの車が高性能と評価されました。しかし、近年は厳しい経営状況に直面しています。そのきっかけの一つが、2018年に起きたカルロス・ゴーン元会長の逮捕事件です。この事件をきっかけに、社内の秩序が大きく揺らぎ、経営陣の入れ替わりが頻繁に起こり、安定したリーダーシップを欠く状態が続きました。
また、アメリカ市場ではハイブリッド車の人気が高まる中、日産はその需要にうまく対応できず、競合他社に遅れを取ってしまいました。さらに、中国市場では、BYDなどの新興メーカーが低価格の電気自動車(EV)を展開する中で、日産は市場の変化についていけず、シェアを奪われる結果となっています。
大規模なリストラ計画で立て直しを図る

こうした経営危機を受けて、日産は2024年11月に大規模なリストラ計画を発表しました。この計画では、世界中で9,000人の従業員を削減するほか、生産能力を20%縮小する方針を示しました。具体的には、現在年間500万台の生産能力を、実際の販売台数である340万台に合わせる形で調整することを目指しています。また、コスト削減にも力を入れており、固定費を3,000億円、変動費を1,000億円削減する計画が進行中です。
これらの取り組みは、特にアメリカや中国市場での販売不振への対策として実施されています。リストラは厳しい選択ですが、経営の立て直しには避けられない一歩とされています。
ホンダとの提携で未来を見据える
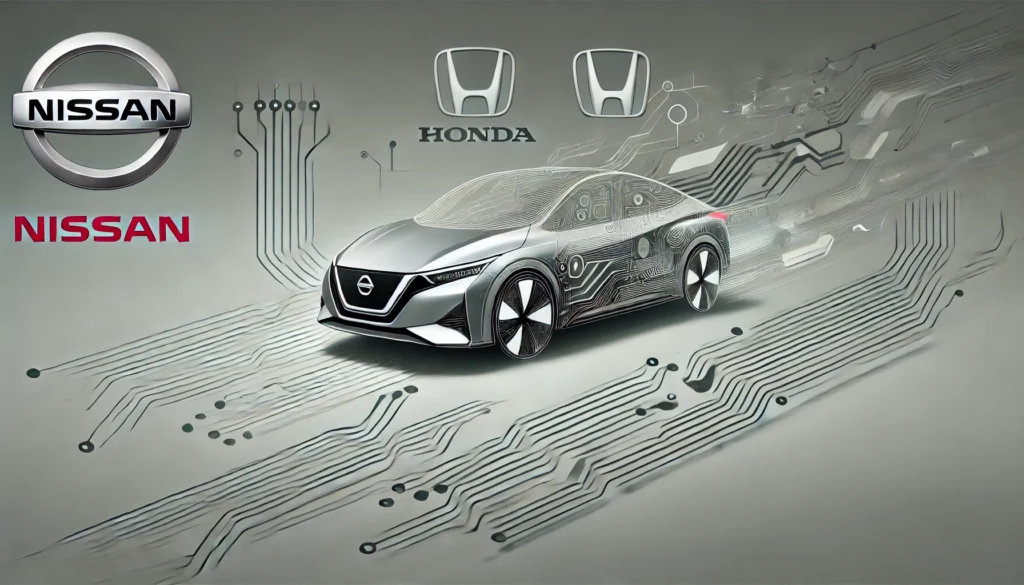
さらに、日産は電気自動車(EV)市場での競争力を高めるため、ホンダとの提携も進めています。2024年12月には、両社がEVの共同開発やソフトウェアプラットフォームの協力に関する覚書を締結しました。この提携は、今後急速に拡大すると予測されるEV市場での生き残りを目指す戦略的な動きといえます。
しかし、日産は依然として財務的な課題を抱えており、一部の専門家からは、外部からの支援がなければ12ヶ月以内に深刻な経営危機に直面する可能性があるとの指摘もあります。これからの経営判断が、日産の未来を左右する重要なポイントとなるでしょう。
技術だけでなく、消費者ニーズに目を向ける重要性

これらの動きから見えるのは、技術革新だけでは企業は成功できないという現実です。日産が誇る技術力は素晴らしいものですが、消費者のニーズや市場の動向を無視すると、競争力を失うリスクがあります。日本企業全体にも、独自技術へのこだわりが強い傾向がありますが、最終的には顧客の声を聞き、柔軟に対応する姿勢が重要です。
日産の事例は、技術開発と市場適応のバランスが取れていないと、どんなに優れた技術があっても競争で負けてしまうことを示しています。これから日産が「技術の日産」として再び輝くためには、市場を冷静に見極め、顧客の信頼を取り戻す努力が欠かせません。