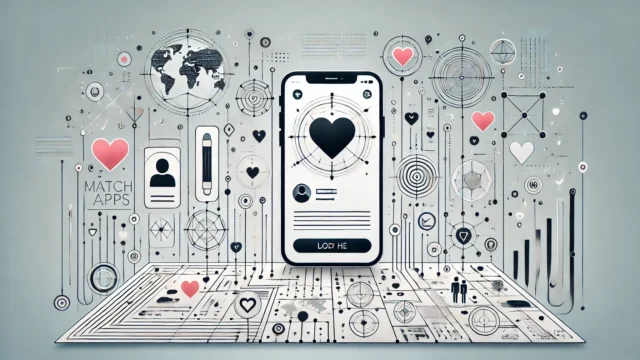振込手数料の値上げはなぜ起こるのか?

最近、都市銀行が他行宛て振込の手数料を大幅に引き上げています。その理由はいくつかありますが、大きな要因の一つが「銀行業務の効率化とコスト削減」です。
昔に比べてキャッシュレス決済が普及し、現金を扱う機会が減ってきています。そのため、銀行はATMや窓口での業務を減らし、インターネットバンキングやスマホアプリへ移行させたいと考えています。銀行の窓口やATMで振込をするには、人件費や設備費用がかかるため、コストが高くなります。
また、振込には詐欺やマネーロンダリング(資金洗浄)といった犯罪を防ぐための対策も必要です。これにはシステムの強化や監視体制の整備が必要であり、銀行側の負担が増えています。こうした背景から、従来の安い振込手数料を維持するのが難しくなり、大幅な値上げが行われました。
三菱UFJ銀行とりそな銀行の事例
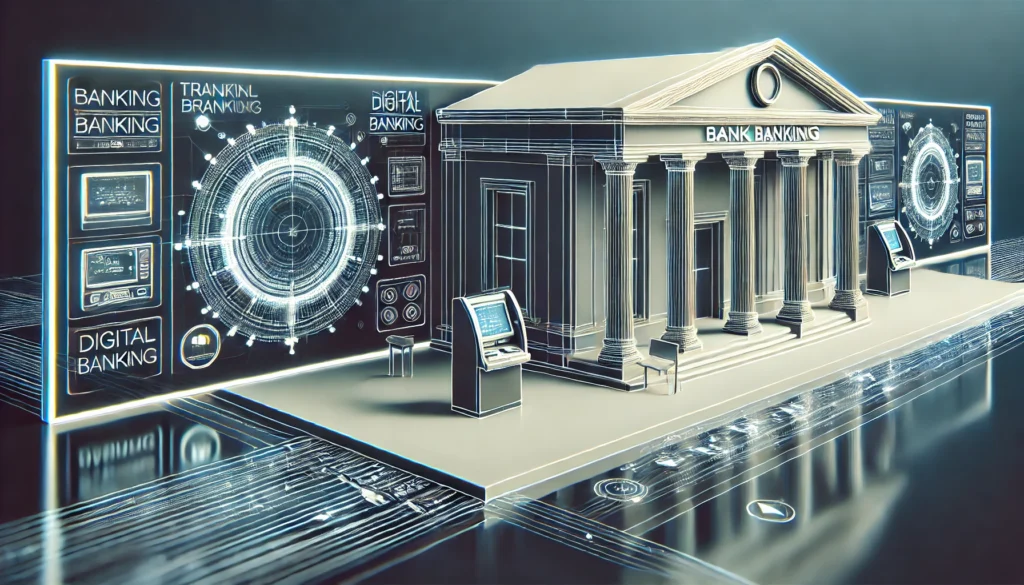
都市銀行の中でも、すでに振込手数料の引き上げを実施している銀行があります。例えば、三菱UFJ銀行は2023年10月2日から、窓口での他行宛て振込手数料を990円に改定しました。以前は数百円程度だった手数料が、一気に1000円近くまで上がりました。
また、りそな銀行も2025年4月1日から、窓口やATMでの振込手数料を引き上げると発表しています。これは、利用者にインターネットバンキングやスマートフォンアプリを利用してもらうための施策の一環と考えられます。
銀行にとっては、窓口業務を減らし、より少ない人員で運営することでコスト削減が可能になります。しかし、利用者にとっては大きな負担となるため、特に高齢者やデジタルツールに慣れていない人々から不満の声も出ています。
デジタル化のメリットと課題
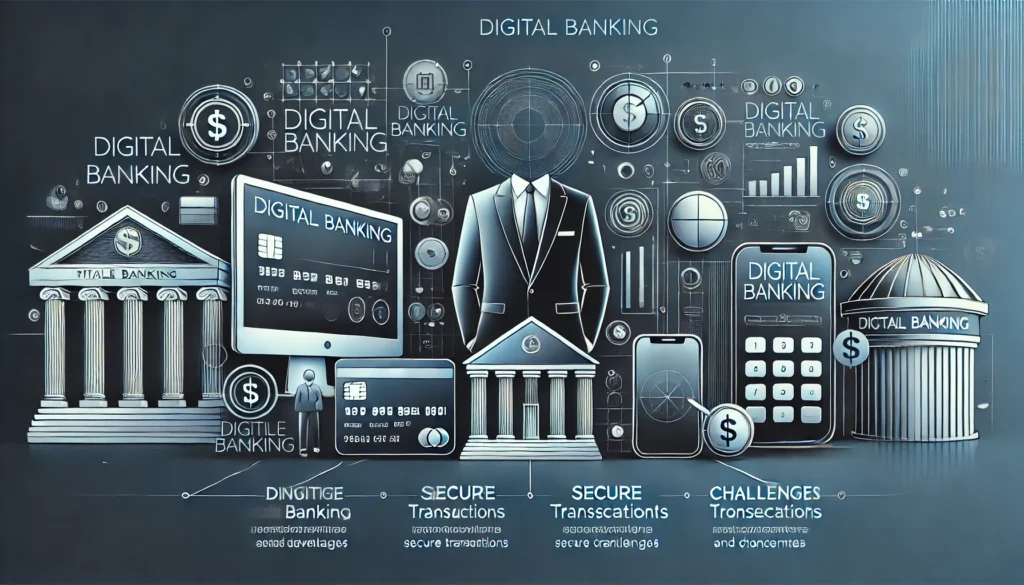
銀行がデジタル化を推進することで、さまざまなメリットがあります。例えば、インターネットバンキングを利用すれば、手数料を安く抑えることができる場合が多いです。窓口やATMでは990円かかる振込手数料も、ネットバンキングを利用すれば無料~数百円程度で済むことがあるため、利用者にとっても経済的なメリットがあります。
また、銀行にとっても、窓口対応を減らせば人件費や設備費を大幅に削減できるという利点があります。そのため、今後も銀行はデジタルサービスの充実を進め、対面サービスを縮小していく可能性が高いです。
しかし、このデジタル化の流れには課題もあります。例えば、高齢者やデジタル機器に不慣れな人々にとっては、大きな負担となります。スマホやパソコンの操作が苦手な人にとっては、インターネットバンキングの利用が難しく、結果的に高い手数料を支払うしかない状況になってしまいます。銀行側は、こうした人々のために、より使いやすいサービスやサポート体制を整えることが求められています。
窓口銀行の未来とネット銀行との競争

都市銀行が窓口業務を維持するには、多くの人件費や設備費用がかかります。これは、ネット銀行と比較すると大きなハンデとなります。ネット銀行は店舗を持たず、すべてのサービスをオンラインで完結させるため、運営コストを抑えることができ、その分振込手数料なども安く設定できます。
そのため、都市銀行が生き残るためには、単に手数料を下げるのではなく、対面でしか提供できない付加価値の高いサービスを強化することが重要です。例えば、住宅ローンや投資相談、法人向けの金融サービスなど、専門的なアドバイスが必要な分野では、対面サービスの価値が高まります。
また、利用者にとっては、銀行を選ぶ際に、手数料だけでなく「どのようなサービスを受けられるか」を重視することが大切になります。ネット銀行は手数料が安い反面、直接相談できる窓口がないため、専門的なアドバイスを受けたい場合には都市銀行の方が適しているかもしれません。