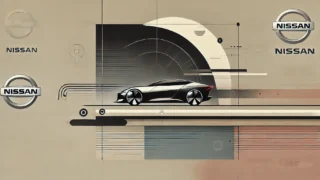ふるさと納税ってどんな制度?

ふるさと納税は2008年に始まった制度です。自分が応援したい地方自治体に寄付をすることで、住民税の一部が控除される仕組みになっています。そのお礼として、寄付した自治体から地域の特産品がもらえることが大きな魅力です。
この制度は、地方自治体の財源を増やし、地域を元気にすることを目的としています。例えば、寄付金を使って学校を直したり、自然を守る活動をしたりと、いろいろな使い道があります。寄付する人は、生まれ育った地域や好きな地域を選ぶことができるので、自分の「地元」を応援する気持ちを形にできます。
返礼品の競争と制度の課題

ふるさと納税が始まったころ、返礼品は地元の名産品やおいしい食べ物などが中心でした。しかし、制度が広まるにつれて、商品券や高級家電といった地域に関係のない返礼品が増えてきました。これが原因で、自治体間の競争が激しくなり、本来の目的が薄れてしまうケースも増えました。
返礼品の豪華さが寄付額を左右するようになり、自治体の負担も大きくなりました。寄付金の大部分が返礼品の購入や配送に使われるようになると、地域を支えるための資金が十分に残らないという問題が指摘されました。
ポイント付与の禁止と規制の強化
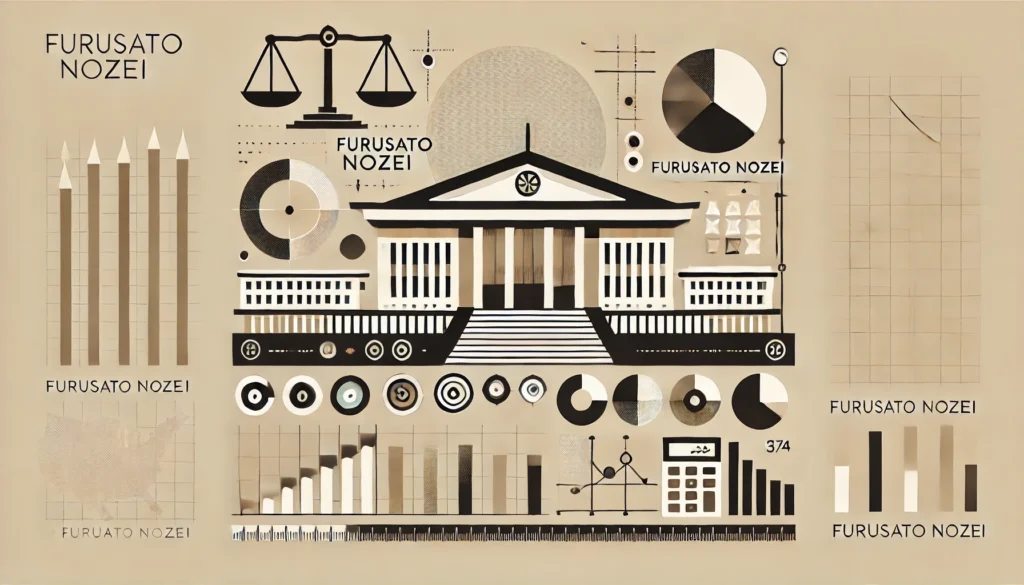
こうした状況を受けて、総務省は2019年に「返礼品を寄付額の3割以下で地元産品に限定する」というルールを作りました。それに加えて、2025年10月からは楽天や他の仲介サイトが行っているポイント付与が禁止されることになりました。
ポイント付与は利用者にとってとてもお得な仕組みでした。「ふるさと納税をするとポイントがもらえる」という特典があったため、多くの人がこの制度に興味を持つきっかけになりました。一方で、「どのサイトが一番ポイントをくれるか」という争いが起き、本来の目的である「地域を支援する」という意義が軽視されるようになったとの批判もありました。このため、総務省はふるさと納税制度を元の趣旨に近づけるため、ポイント付与を廃止することを決めたのです。
ポイント付与禁止をどう考える?

ポイント付与の禁止については賛否両論があります。「ポイントをなくすべき」という意見もあれば、「利用者にとってのメリットを奪うべきではない」という声もあります。筆者としては、ポイント付与がふるさと納税に興味を持つ人を増やした効果は少なくなかったと考えています。
例えば、「ふるさと納税で楽天ポイントがもらえるなんてお得!」という理由で寄付を始めた人も多いでしょう。競争そのものが悪いわけではなく、上手にルールを作ることで利用者も自治体も得をする仕組みが考えられるかもしれません。
今後は、利用者がふるさと納税をもっと使いやすく感じられる工夫と、自治体が地域活性化に役立つ資金を得られるバランスをとることが課題です。この制度が引き続き多くの人に利用され、地域の未来を支えるものになるよう、新しいアイデアや取り組みに期待したいですね。